こんにちは。塾長です。
結婚をきっかけに、家族が増える事を想定して車を家族用のものに替えようと考えている方は多いのではないでしょうか。
私、塾長もそういった考えの一人であります。
今回は「家族想いな車」をテーマに、ランキング形式で解説していこうと思います。
家族想いな車ランキング1位~5位

早速ランキングの発表です。
今回のテーマに則り、現代の一般家庭に必須条件として「両側スライドドア」、そして後述しますが、「ハイブリット設定可能」の車をまとめました。
「家族」のライフスタイルにどう応える車が選ばれているのでしょうか。
1位 トヨタ VOXY/NOAH/エスクァイア

「父になろう」というキャッチコピーでデビューしたVOXYも3代目。キャッチコピーの通り、お父さんが主役のファミリーカーとして高い支持を得ています。
ちょっとイカツイ見た目、意外に「カチッ」とした足回り、ママが運転しても見晴らしの良い視界と逞しい走りが懐の深さを見せつけます。
特筆すべきは、その「走り」にあります。
背の高い1BOX型ミニバンは、カーブを曲がる時に「ロール」という横揺れがどうしても発生してしまいます。
そこをトヨタ独自のサスペンション技術が与えられた3姉妹車はロール量が抑えられ、少し硬めでありながら、しなやかな足回りを実現しています。
さらに、ドアミラーの脇やテールランプの側面に配された突起物が空気の渦を発生させ、高速道路の走行での安定性に一役買っています。
「理想的な父親」を車で表現したらこうなる、とトヨタは言っているような気さえしてきますね。
実は、ボクシーも姉妹車のエスクァイアも、ノアをベースに造られているんです。なので、基本的な装備や走りのメカニズムは共通です。
姉妹車のノアはビジュアルが優しく、ママ向けに振られた外見で、同じく姉妹車のエスクァイアはアルファードを思わせる高級感を演出し、若者ウケを意識した顔つきになっています。
3車共に設計統括を水澗英紀氏が務め、内装こそ共通なもののエクステリアの色設定、ヘッドランプの形状、便利機能の采配にこだわりがみられます。
オススメユーザー
- いつまでも「カッコよくいたい」美意識のある方
- 家族を大事にしながらも「走り」にはこだわりたい方
2位 HONDA ステップワゴン

ステップワゴンは、HONDAが家族で乗る車として1996年にデビューして5代目になります。
エンジンの上に座席がある「キャブオーバー」型のミニバンと遜色ない視界でありながら、着座位置が低い乗用車的な要素と低価格設定で一気に人気を獲得しました。
この車の利点は、「とにかく使い勝手を追求している」点にあります。
その目玉設備がわくわくゲートと床下格納3列シートです。

タテにもヨコにも開くドアが今まであったでしょうか。
この機構は、従来のバックドアに横開きの機能を追加したもので、駐車した時に後ろのスペースが狭い時や、サッと荷室にしまいたいものがある時、後ろからの乗り降りに威力を発揮します。
また、床下格納3列シートとの組み合わせは合理的と言えます。
1BOX型ミニバンに多く採用されている跳ね上げ式3列シートだと、せっかくの便利なゲートが台無しになってしまいますからね。
また、中からはもちろん、外からでも簡単に分割格納できる点もユーザー目線を考えられてている装備として重宝されるのではないでしょうか。
オススメユーザー
- 使い勝手をとにかく充実させたい方
- わくわくゲートに魅力を感じる方
3位 日産 セレナ

今、日産が特に力を入れている分野があります。
それが「自動運転」。
すでに世界的に研究・開発が進められ、アメリカのテスラ社は「モデル3」という車種でほぼ実用レベルの自動運転車をリリースしています。(結構なお値段なので、万人にオススメはできませんが)
セレナは、メーカーオプションとなる「プロパイロット」で、高速道路など長時間の単調に巡行するシーンに限定して加減速、ステアリング操作を自動化できます。
これは何より長距離を走るドライバーの負担軽減になるものです。
そのシステムの為か、ドライバーが運転した場合の乗り味がソフト傾向に振られるようで、ロードノイズや微振動が気になってしまうあたり、車体の剛性不足が否めないのでは?との指摘も出ています。
実はこのシステム、厳密には自動運転にはなりません。
この記事↑で詳しく解説していますが、限定的な条件でのみ自動化の効力があることは自動運転レベルで言うと「2」で、正式には「運転支援システム」と言います。
先述したテスラ社のモデル3も「レベル2」で、2020年現在、自動運転とされるレベル3の車は実験段階で、市販化はされていません。
とは言えこの機構、長距離ドライブや首都高のような鬼渋滞のノロノロ運転の負担をかなりの部分で削ってくれる先進技術です。
今後の発展に期待していいのではないでしょうか。
オススメユーザー
- 一定の頻度で長距離を移動する方
- 「走り」にはこだわりがない方
- 自動運転に魅力を感じる方
4位 HONDA フリード

「丁度イイ」をコンセプトに造られたフリードは、コンパクトミニバンの部類でありながら、必要十分な車内空間を有しています。
そのクラスを越えた車内空間のおかげで実現する、1BOXミニバンと同等のシートアレンジも、HONDAの特許技術「センタータンクレイアウト」がなせる業と言えましょう。
本来、中心よりも後方に位置するのが通説となっている燃料タンクを2列目シートの下辺りに持ってくることで、荷室やシートアレンジの自由度が飛躍的に広がっています。
それによって重量配分が最適化されるため、HONDAのお家芸である安全運転支援システム「HONDA SENSING」との相性が抜群であることから、これらは多くのラインナップに採用されています。
また、スライドドアの下を足でかざすと開閉する「ハンズフリースライドドア」がディーラーオプションで選択できます。
便利なオプションが充実しているのは嬉しいですね。
オススメユーザー
- 1BOXミニバン程の大きさを必要としない方
- シートアレンジが多彩なコンパクトミニバンをお探しの方
- 夫婦で運転される方
5位 トヨタ シエンタ

トレッキングシューズをイメージして造られた、トヨタ最小ミニバンが「シエンタ」です。
この車のテーマは「斬新さ」なのではないでしょうか。
ミニバンと言えば、どこか四角形を思わせるような箇所が見え隠れするのに対して、シエンタは全体的に丸みを帯びたスタイリングです。
初代エスティマのパッケージングを彷彿とさせますね。
そして、斬新さを意識したシエンタ最大の強みは「芸達者」であることなんです。
まずはミニバンのお家芸、シートアレンジ。
シエンタは最大7人乗りですが、3列シートが跳ね上げ式ではなく、2列目シートの下に潜り込ませるユニークな格納方式をとっています。
最初は面倒に感じますが、女性でも軽々と動かせるように設計されているので、慣れてしまえば広いフルフラットなスペースを難なく作ることができます。
そして、雨の日に威力を発揮する「オープン&クローズ予約機能」。
まずリモコンのボタンでドアオープンを予約、車に近づくと勝手に開錠と共にドアオープン。閉める時も、電動ドアが閉まり切る前にロックボタンを押すことでスライドドアが閉まり切ると同時にロック。
従来の電動スライドドアだと、閉まり切るまでロックはできませんでした。
そのためロックするには閉まるまで待っていなければならず、時間にして数秒なんですが、雨の日は特に長く感じるものでありました。
それがロックを予約することで閉まり切る前に車から離れることができ、開錠を予約することで車に近づいただけでドアが開くという離れ業が可能になりました。
まさに「自動ドア」ですね。
そのほか、衝突回避などの先進予防安全設備のToyota Safety Senseが全てのグレードに設定可能なことや、最大16種類のカラーバリエーションなどシエンタの芸達者は多岐にわたります。
意外とコスパは優秀なんですね。
オススメユーザー
- 1BOXミニバン程の大きなサイズを必要としない方
- 都会的でオシャレな車が好きな方
- 夫婦で運転される方
- 「走り」にこだわりを持たない方
ハイブリッド仕様のススメ
冒頭でも述べましたが、ハイブリッド仕様を必須条件として盛り込んだのには理由があります。
それは、「新車登録から13年経過すると自動車税がワンランク上に跳ね上がる」ことが法律で決まってしまったからです。
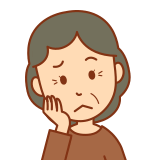
「なら、ハイブリッドでも一緒でしょ?」
それが違うんです。
法律には、より細かい内容を付け加えるために「但し書き」が付くことがあります。
この「13年モノ増税」(←塾長の個人的なネーミング)にも但し書きはあり、「ハイブリッド車や電気自動車などの環境に配慮された自動車の場合は13年を経過しても自動車税を据え置く」とあります。
こちらの記事↑で詳しく解説していますが、正式名称を「グリーン化特例」と言い、環境に配慮されたエコカーの普及を目的に制定された制度で、広く知られている「エコカー減税」もその一部です。
エコカーの新車登録から最初の1年のみ減税が受けられ、それ以降は所有する限りガソリン車と同じ税率の支払い義務が課せられます。
このカテゴリーを調べれば調べる程ツッコミどころが出てきてしまうのですが、法律で決まってしまった以上、法律の改正がされない限り国民は逃れられません。
なので、できるだけポジティブに捉え、最大限使っていくしかないとすれば、ハイブリッド仕様は外せない条件となるわけです。
家族想いな車~番外編~

代表的な家族のライフスタイルを想定して有用な車を紹介してきましたが、ここで番外編にいきましょう。
番外編ですが、家族という意味合いに於いては大事なことですので、車選びの考えの一部にでも留めておいて損はないと思います。
福祉車両と言う選択

家族は、夫、妻、子供。だけではありませんよね。たとえ離れて暮らしていても、祖父母も立派な家族です。
孫ができる年齢になれば、身体的な衰えが否めないことも大いにあります。
そうなったときに、例えば単純に「車の後部座席に乗る」という若くて健常者ならば造作もない事が「腰が曲がってグリップに手が届かない」「足が上げられなくてステップに中々乗れない」などの障壁になったりすることが往々にしてあるようになります。

そんな家族のバリアフリーを車に持ってきたのが「福祉車両」です。
スポーツカーなどの特殊な車両を除き、現在市販されているほとんどの車に福祉車両の設定があります。
なので、「福祉車両のために狙っていた車をあきらめざるを得ない」なんてこともないでしょう。
福祉車両のメリット&デメリット
そんな福祉車両ですが、もちろんメリット&デメリットがあります。
デメリットとしてまず、車両自体が割高であることが挙がります。
これは車椅子を電動で格納する装置や、シートが車外まで移動するリフトアップ機構のためで、道理といえば道理ですね。
そして、車重が重くなる。
これも上記に付随してのことで、致し方ない事でありましょう。
車椅子の格納装置があるタイプに言えることですが、荷室スペースが制限されることもデメリットとして挙がります。
1BOXミニバンならまだ容量を確保できる余地はありますが、軽のハイトワゴンなどの場合は工夫しなければならなくなるでしょう。
しかし、それらをカバーしてお釣りがくるくらいのメリットがあるんです。
まず、税金の優遇制度。
- 自動車税の減免制度
- 自動車取得税の減免制度(現在自動車取得税自体廃止)
- 新車・中古車問わず福祉車両の購入にかかる消費税が非課税
以上が主だった税金の優遇制度です。ハンディキャップのある方に対してジェントルな措置が施されると言って良いでしょう。
それに比べて健常者に対する徴税は「いじめ級」ですがね…
更に、優遇制度はそれだけにとどまりません。
- 福祉車両の購入資金の貸し付けや補助
- 福祉車両に改造した時の改造費の助成
- 有料駐車場代の割引
- 燃料代の助成
- 高速道路など有料道路の割引
- 福祉車両優先・専用駐車場に駐車可
以上、実に手厚い優遇制度がハンディキャップを持った人や、体の不自由な高齢者の助けとなります。
それだけ介護というのは大変ということですね。
因みにですが、国の助成制度は全国共通ですが、一部地方自治体が管轄する制度もあるため、詳しくはお住いの市区町村の福祉課にお問い合わせいただくと確実です。
どちらにせよ一定の条件があるので、それも併せてお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
家族のための車に求められるもの

「家族を持つ」ということは、違った人生を歩んできた者同士が新たな命と共に新しい家族として生きていくことです。
ファミリーカーは、そんな家族の「手助け」ができる車なんです。
その「手助け」とは、乗る人全てに対しての「思い遣り」であると言えるのではないでしょうか。
家族サービスで運転するパパの負担を少しでも軽くする「運転支援システム」。
予測が難しいお子さんのアクシデントにも対応するママのサポートになる装備「両側電動スライドドア」。
まさかの事態でも乗員の命を守る「エアバッグ」、まさかの事態そのものを回避するシステム「自動ブレーキ」。
そして、体のハンディキャップを持った家族のための「福祉車両」。
どれをとっても、相手を思い遣る心が全てであることがおわかりいただけたでしょうか。
この記事があなたの選択の一助になれば、幸いです。




