こんにちは。塾長です。
「目的地まで無事故で到達する」のは難しいですか?
条件にもよるのでしょうが、距離が長くなるほど、交通量が多いほど、運転歴が浅いほど無事故の難易度は上がる傾向にあるのが常と言えましょう。

そこで今回は、「安全な運転」について深堀りしていこうと思います。
安全運転の心得

運転免許をとる時、大部分の人が教習所に通うものと思いますが、教習所で教わる事は、「運転の基礎でしかない」ことを理解する必要があります。
「教習所で習うことが運転の全てではない」のです。
一体どういうことなのか、順序だてて解説していきます。
運転は何より「経験値」がモノを言う
確かに教習所で習うことは運転する上で欠かせない大事なモノですが、それだけで「安全運転」が継続できるかというと、ちょっと力不足な感じは否めないでしょう。
なぜなら、交通状況は刻一刻と変化していくものであり、データ化するのはAIなどでない限り無理があるからです。
ならば、我々人間が安全運転を続けていくにはどうすればいいのでしょうか。
それには、「経験を積む」しかありません。
多くの経験を積むことで、潜在的に「危険予測」が可能となり、事故や危険を未然に防ぐことができるようになります。
まずは「運転あるのみ」

「習うより慣れよ」という言葉がある通り、自分の感覚で経験していくことこそが最も効率的な「道」なのかもしれません。
その経験の鍛錬の道には、大別して2つのタイプがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
優良ドライバーと言われる人たちは、えてしてこの2つを鍛えているものです。
タイプ①運転回数の経験
これは分かり易いですね。運転の回数、多くの場数を踏むことで「交通状況の先読み」が可能となり、「運転の上手い人」と評されたりします。
そんな「運転の上手い人」も、最初からそうだったわけではありません。
誰でも最初は初心者マークを付け、おっかなびっくりのデビューだったでしょう。
ですが、運転に慣れてしまえば、落ち着いた運転ができてきます。
そこまでのレベルになれば、心に余裕ができ、周りの状況も冷静に見ることもできるでしょう。
そこからが更にレベルアップするか「漫然運転」に落ち着くかの分かれ目になります。
「遠くを見据える」
車の動きというのは「シンプル」であることにお気づきでしょうか。
交通の流れに沿って走行している時、「有り得ない動き方」をしている、あるいはしそうな車、歩行者、自転車はシグナルを発しているものです。
それを早い段階で察知するには、「遠くを見る」ことが重要です。
ベテランドライバーやプロの運転手は前方を遠くに見据え、道幅が狭くなったら車間を開ける、雨の日は視界を確保して晴れの日よりも慎重に運転するなどして交通状況を把握し易くしています。
遠くを見るとは述べましたが、見るのは遠くだけではありません。
遠くの視点をベースに少し手前の状況も確認できるようなポジションがあります。
日々の運転の中で、「ストレスなく一番見渡しやすいポイント」を探しましょう。
また、こういった達人の「テクニック」を盗むのも有効です。
もし身近にベテランドライバーがおられるなら、是非運転を観察させてもらいましょう。
タイプ②精神的寛大になる鍛錬
俗に言う「ハンドルを握ると人が変わる人」は結構な割合で存在します。
それは、閉ざされた空間において何かしらに集中している時は自身の率直な感情が露わになり易いためと言われています。
野球やサッカーの試合のテレビ中継、コメディー要素強めのバラエティー番組を見ているときなどはその典型でしょう。
選手の一挙手一投足に一喜一憂したり、タレントのユーモアにツッコミながら大笑いしたりするのは多くの人が思い当たることでしょう。
車の運転もそれらに準じたもので、ほぼネガティブな感情が出てしまうことが多いようです。
中には悪態をつくだけに留まらず「煽り運転」にまで及んでしまうケースも少ないとは言えなくなってきました。
こちらの記事⇩で「煽り運転」を詳しく解説しています。
「許す」という心構え
ネガティブな感情は時に暴走してしまう危険なモノです。
「俺の前に割り込みやがって」「こっちが正しく走ってるのにあいつはルールを無視した」
など、ある種「俺様何様」的な感情が沸き立ってくるのではないでしょうか。
そんなネガティブな感情も、多くの場合「強すぎる正義感」からくるものでありましょう。
ともすれば、考え方を変える事で対策できる余地があります。
つまり、「寛大になる」事で自分の優位性を確立させる、という手法です。
とはいえ、明日から別人になったかのように変わることは難しいでしょう。
なので、まず「許してあげよう」という心構えを持つことで、自尊心を損なわずに考え方を寛大にしていく足掛かりになり、ジェントルな運転にシフトしていき易くなる一つの方法としてアリなのではないでしょうか。
するべきこと、すべきでないこと

安全な運転のためには、するべきことと、するべきではないことがあります。
それらをきちんと理解することで、運転に対する見方が変わってきます。
するべきこと 基本に忠実
教習所で習うのは運転の基礎であることは先に述べた通りですが、慣れてくると疎かになりがちなものでもあります。
代表的なものを以下にまとめてみました。
- 車に乗る前の進行方向の確認
- 車に乗ったらするシートベルト
- 発進の直前にする左右の確認
- 右左折間際の後方目視確認
- 車を降りる手前のサイドブレーキ
どれもちょっとした手間のかかるものばかりですが、その手間で大事故から身を守れる大きな「転ばぬ先の杖」となることでしょう。
是非めんどくさがらずに実行していきましょう。(これらには罰則のあるものもありますので…)
すべきでない事 ながら運転
運転に慣れてくると、余裕が出てきます。
しかしその余裕が行き過ぎてしまうと、「驕り」や「放漫」、「過信」などという形でよろしくない方向に向かってしまいます。
運転は、刻々と変化する交通状況に随時対応し、本来は車を降りるまで気が抜けないものです。
なので、運転に集中するために「ながら運転を控える」ことで上記のような邪な考えを払拭するキッカケになるかもしれません。
「飲みながら」「食べながら」「吸いながら」…罰則はなくても、運転中はあまり望ましくない行為でありましょう。
勿論「スマホしながら」は普通にアウトです。
運転以外に注意をそがれる可能性のあるものはすべきではありませんね。
こちらの記事も併せてどうぞ。
実はドライバー任せの「道路交通法」

教習所では、運転に関する基礎的な事を軸に、関係法令も学習します。
一般に「道路交通法」と呼ばれているもので、制限、義務、罰則があります。
例えば信号機
道路交通法のほとんどが「ドライバーの判断に委ねられている」事をご存じでしょうか。
教習本では難しい文言で説明されていますが、例えば「信号機」。
赤は「止まれ」、青は「進むことができる」、黄色は「基本止まれ。止まり切れない場合に限り進むことが許される」。
赤は分かり易いですね。信号が赤の時は止まらなければなりません。
間に合わなければ、「前方不注意」で罰則の対象になり得ます。
青が意外と意図を含んだ指示で、「前方が渋滞や片側工事などで進めない状態の時は進んではならない」という意味が隠れています。
そして黄色は「基本止まれ」なので、止まれる状態であれば止まらなければなりません。
ただ、黄色の時に既に交差点に進入していた場合などは、そのまま通過が許可されています。
ムリヤリ止まれば追突を誘発する危険があり、止まれたとしても左右の交通の邪魔になるからです。
ドライバーの判断力
青は進めるなら進め、黄色は止まれなければ進め。
この二つ、ドライバーの判断に依存している代表です。
誤解の無いように言いますと、それが悪いということではなく、交通の性質上一番効率的に浸透する方法がこれしかないのではないかな、と思います。
これだけでなく、他にも噛み砕けばドライバーの判断に丸投げしたような「決まり」が多数存在します。
勿論、法務省の手抜きでもなければ国土交通省の横着でもありません。
これは、「ドライバーの判断力の質」を高めることが求められている事になるのです。
まとめ

今回は安全な運転にフォーカスしてみました。
具体的なやり方以前の「本質的なマインドセット」ができましたでしょうか。
意識を高めて維持するのは、とても「めんどくさ」くて「疲れる」ものです。
しかし、それができるのは人間しかいません。
自動車を運転できるのも人間だけです。
事故という便利な文明のデメリットを出さないように使うのは人間の責務と言えましょう。
この機会に当記事が参考になれたら幸いです。




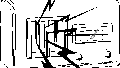
コメント
[…] 安全運転するにはコツがあった。事故らないための極意を紹介 […]