こんにちは。塾長です。
ここ最近の科学産業技術の発展には、目覚ましいものがありますよね。
車に関してもそれは言えるのではないでしょうか。
特に、最近話題になっている「自動運転」。
いまだ賛否両論あるようですが、もしこれが実現されれば、私たちの暮らしはどのように変わってくるのでしょうか。
ちょっとワクワクする反面、不安になってしまう事もあるでしょう。
そこで今回は「自動運転」についてなんですが、まだ不完全な領域でもあるので、考察も織り交ぜて解説していこうと思います。
自動運転は既に普及している!?

実は、自動運転の思想は日本だけの事ではないんです。
アメリカをはじめ「先進国」と言われる国々は、今こぞって自動運転に力を入れています。
既に「テスラ」という自動車メーカーは「モデル3」という車種で実用レベルの自動化に成功した車がアメリカで実走していたりもしますが、日本では法整備も含め、まだまだ実用化には至っていないのが現状のようです。
日本で採用されているもの
とはいえ、我が日本でも「部分的に自動化した車」は存在します。
代表的なものに「クルーズコントロール」「レーンキープアシスト」「自動ブレーキングシステム」などがあります。
クルーズコントロール
一定の速度を設定することで、アクセルを踏まなくてもスピードがキープされる機能で、主に高速道路などでドライバーの負担軽減に威力を発揮します。
レーンキープアシスト
車線から車体がはみ出た場合、警告音と共に正しい位置に戻ろうとする機構です。カーブの多い所で重宝されます。
自動ブレーキングシステム
センサーにより、車速に対して障害物がぶつかりそうになると自動でブレーキングしてくれる装置です。
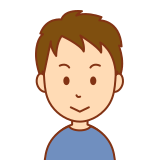
スバルの「アイサイト」など、名称が付いている場合もあるよね。
これにより、追突、誤発進による事故が対策できます。
自動運転に係わる問題点

想像でしかなかったような未来的な事が現実になろうとしていますが、現実化するには、現実的なことを整えなければなりません。
そうでなくては、「こうなったら、どうするの?」という不安が拭えないからです。
まして、車は人という命を運ぶもの。「想定外だった」では済まされません。
実用化されれば、私たちの暮らしは間違いなく便利で豊かなものになる事は容易に想像できますが、それにはシッカリした地盤が固められているからこその物であるべきと思います。
そうでなければ、昭和初期のように「車は走る棺桶」と揶揄されるでしょう。
事故の責任
事故の責任は、事故を起こした当事者にあります。
完全に自動化したならば、運転免許を持たない人だけでも乗ることができます。
そうなると、責任の所在は所有者、並びに自動車メーカーにかかってくることになると思われます。
そのためか、現段階ではトヨタでさえ「飽く迄ドライバーのアシスト」という理念で開発を進めています。
この問題に折り合いが付かない限り、完全な自動化は難しいと言わざるを得ないでしょう。
失業者の対策
車が完全に自動化されればどうなるか、運転をする必要がなくなるため、まず「運転士」が職を奪われます。
悲しい事ですが、便利で豊かになる裏ではこういった大量の失業者を出してしまうことが考えられます。
企業努力やアイデアで合理的な仕組みを再構築して、経営と労働のバランスをとっていくことが求められる時代になってくるのではないでしょうか。
運転免許の存在意義
もしも自動運転車がスマホのように普及すると、不要になってくるのが「運転免許」です。
完全に自動運転する車は、アクセルペダルやブレーキペダルはおろか、ハンドルすらありません。
そんな車が町中を走ることになります。
つまり、人はただ乗るだけで、行先を入力して出発ボタンを押せば目的地到着まではお任せ。
もっと言えば、子供だけでも利用できるんです。
ともすれば、運転をするための資格証だった運転免許証は、単なる「身分証明書」にしかならなくなることが予測されます。
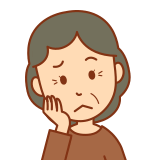
免許取るのに高いお金を払った上にたくさん勉強した私達って…
耐久性の懸念
自動運転を下支えしているのは、たくさんの「高性能センサー」達です。
彼らの一つでも故障してしまえば自動運転は成り立たず、部類によっては最悪の事態を引き起こしかねない危険を孕んでいると言えるでしょう。
技術革新がかなり進んでいるとはいえ、「先進技術は高性能なほど壊れやすい」という見方も根強く、「耐久性」については多すぎるくらいの実走テスト~改善を繰り返すなどして、耐久性を確保するのは今後の大きな課題と言って良いのではないでしょうか。
悪天候時の対応
意外と見落とされがちなのが、悪天候時の対応です。
普通の雨や風などなら問題ないかもしれませんが、大雪ともなれば話は違ってきます。
タイヤにチェーンを巻いたり、スタッドレスタイヤに換装したりしなければなりません。その判断や行使が搭乗者に求められます。

その頃には、全天候型のタイヤが開発されているのかな?
また、2011年(平成23年)3月11日に発生した「東日本大震災」。それによる津波は、まるでパニック映画のワンシーンのように日本中を恐怖に陥れ、自然の脅威をまざまざと見せつけられた出来事として記憶にも新しい事と思います。
もし、この時に自動運転が普及していたらどうでしょう。
すぐそこまで海水が来ているのに車は止まらず、操作もできず、車が流されているのに水害で電気系統がショートしてロック解除ができず、出る事すらできなくなる。といったことが考えられます。
考えるのも嫌になりますが、こういったことを考えずして地震大国日本での自動運転の普及は有り得ない、とも言えるでしょう。
自動運転化で消える職業

自動車が普及した裏では、それまで移動手段だった馬車や人力車が無くなっていきました。このように、これまでの常識がひっくり返るほどのモノが普及すると、必ず衰退するモノが出てくることは歴史が証明しています。
人が操る車が、操らなくて良くなったらどうなるのでしょう。
今後消えゆくであろう職業を挙げてみました。
運転士
車が「運転するモノじゃなくなる」ことで一番に白羽の矢が立つのが「運転士」でしょう。
今はまだ人の手が不可欠ですが、自動運転に対する世界の熱量からすれば、そう遠くない未来、無人トラックが普通に走っていたりするかもしれません。
教習所
運転しなくて良くなる、ということは、わざわざ免許を取る必要がなくなる、ということになります。
つまり、教習所の存在が危ぶまれるのです。
意外と知られていませんが、運転免許は「国家資格」ですので「身分証明」の役割もあります。
が、身分証のために教習所に通うのはナンセンスになり、「運転をしたい人」や「バイクに乗りたい人」向けの施設になりそうです。
ゴミ収集員
自動運転の広がりは普通車に留まりません。
トラックにも導入の流れが先進各国で見受けられます。
ルートが決まっているゴミ収集も、「フックロール」というコンテナを収容、設置できるトラックが自動運転になれば、設置されたゴミコンテナをフックロールのトラックが自動で回収することも可能になるでしょう。
ただ、現状のコンテナは大きく、設置も回収もそれなりのスペースを必要とするので、コンテナの小型化、フックロールの小回り化が課題となってくるでしょう。
自動運転にはレベルがある

自動運転といっても、いきなり全部自動になるわけではありません。
自動運転に限った事ではないのですが、「段階」というものがあるんです。
早速みていきましょう。聞いたことがある名前があるかもしれませんね。
レベル0
これは自動運転化がされていない、今まで通りの車で、ドライバーが車における全ての操作を担います。
当然免許証もいりますし、事故の責任もドライバーにかかってきます。
ABSやバックソナーなどはこのレベルの部類とされています。
レベル1
システムが「ハンドル操作」「加減速」のどちらかをサポートする場合に該当します。
先にも触れた「レーンキープアシスト」や「自動ブレーキングシステム」「クルーズコントロール」などがこれに当たり、これらのどれか一つが搭載されている状態を言います。
レベル2
システムが「ハンドル操作」「加減速」の両方を制御する場合に該当します。しかし、実はここまでは「自動運転」とはならないのだそうです。
よくよく考えてみれば、運転免許を持つ人がする通常の運転は自動ではなく、自動化のシステムも「特定の条件下で作動するモノ」だからです。
厳密には「運転支援技術」と呼ばれますが、便宜上「自動運転レベル2」とされることもあります。
冒頭で紹介したテスラ社のモデル3はこの部類になります。
レベル3
高速道路などの特定の場所に限定して「運転に係わる全ての制御を担当する」のがこのレベルです。
ここで初めて「自動運転」の部類になります。
ただし、システム異常や、想定外の緊急事態の場合はドライバーが対応しなければならず、免許保持者が運転席に着席している必要があります。
レベル4
高速道路などの特定の場所に限定して「運転に係わる全ての制御を担当する」のはレベル3と同じですが、緊急時の対応もシステムが行うのがレベル4です。
自動運転中はタクシーの後席に乗っているような感じになってくるでしょう。
このレベルに達しているのはコンセプトカーや実験車両でしかなく、現時点での市販はされていません。
レベル5
場所の制限は一切なく、運転に係わる全ての制御を担当、緊急時の対応もシステムがこなす「自動運転の究極バージョン」です。
なので、アクセルやブレーキのペダルはおろか、ハンドルすら無いデザインになるでしょう。
アメリカのテスラ社では、2020年中ごろにこのレベルの車両を実現させる目標を掲げています。
自動運転化に合わせ法律が変わった

自動運転が中々普及されない原因の一つが、「法律の整備」にあると言えるでしょう。
自動車に関する取り決めの「道路交通法」では、刻々と変化する交通事情にも対応した決まりがたくさん定められています。
ところが、まだ実験段階とはいえ、今までにない変化がくると従来の法律では対応が出来ず、事故やトラブルの処理に多大な悪影響をもたらしかねなくなります。
そこで、いづれは来るであろう「自動運転車の普及」を考慮した新法律が制定されました。
スマホや漫画を読める
これは自動運転がされている時に限定適用されるものですが、「スマホや漫画、週刊誌などの書物を見てもいい」となりました。
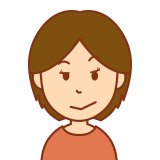
「なら、自動運転の時にパソコンで仕事したりできるんだ?」
それがそうもいかないんです。
飽く迄「見る」のを許されているわけであって、「操作」までいくとアウトなんだそうです。
なので、スマホでゲームはアウト、スマホでニュースを読むのはセーフ、ということになります。
事故の責任
事故というのは、「事故を起こした人」が存在し、ほぼ運転手がそれに当たります。
が、自動運転となると、所有者、使用者共に運転をしていないわけなので、事故の責任の所在がハッキリしていませんでした。
そこで2019年12月に道路交通法と道路運送車両法が改正され、「自動運転中(レベル3)の事故の責任の所在は「ドライバーに課せられる」ことが明文化されました。
今後は、それに向けた保険商品の競争が激化しそうですね。
ここでのポイントは、レベル3としたことです。
自動運転がされない一般道では、ドライバーの運転が必須になります。
レベル4以上の自動運転が実用化された時までは想定しておらず、もし実用化された時は、この法律ごと変わることも有り得そうです。
センサー類の記録が義務化
レベル3の自動運転に必要なセンサー、コンピューター、プログラムなどは、車検で検査される「保安基準対象装置」とみなされ、警察官に要求された時は、自動運転システムの作動状況を記録したものを提示する義務が追加されました。
これにより、常にシステムの記録をすることが事実上義務化され、別媒体に保存するのですが、SDカードやフラッシュメモリーなどは大クラッシュの際に破損するリスクがあるため、オンラインでバックアップをとるのが今後の在り方となってくるでしょう。
なぜ自動運転化が進んでいるか

自動車が普及し、私たちの暮らしは革命的に便利になりました。
さらに現在はトランスミッションがATになった事で車の運転が簡素化され、ドライバーの負担がかなり軽減されています。
そして極めつけが「運転する必要すらなくそうとしている」というから人間の技術革新は恐ろしいものがありますね。
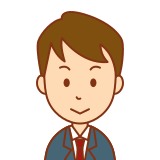
「そこまでしなくても、今のままで十分じゃないの?」
そんな声も聞こえてきそうですが、なぜ、世界は自動運転化を進めているのでしょうか。その理由を解説していきます。
高齢化
特に日本は顕著ですが、世界的に見ても高齢者ドライバーの割合は増える傾向にあると言われています。
身体的な衰えが否めない高齢者ドライバーが引き起こす事として、一番に挙がるのが「ペダルの踏み間違い事故」でありましょう。
まず、高齢者の特徴として「恐いと思ったら動けなくなる」ことが根底にあり、ペダルを間違える➝ブレーキのつもりがアクセルを踏んだ場合、キックダウンにより急加速➝恐怖を感じて体が固まる➝アクセルを踏みつけたままになるので、車が大破するまで暴走
という構図が成り立ちます。
2019年4月に池袋で起きた凄惨な事故はまさにその典型なのではないでしょうか。
こちらの記事↓でも詳しく解説しています。併せてどうぞ。
自動運転化すれば、そもそも運転操作の必要がないわけですから、こういった操作ミスでの大事故はなくなります。
ドライバー同士のトラブル
運転中にあからさまな嫌がらせを受け、危険でもお構いなしに路上に停車させられ、理不尽な言いがかりをつけられ、暴行事件にまで発展する。
そんなドライバー同士のトラブルが多くなっています。
2019年8月10日に茨城県の常磐自動車道で起きた「5発殴打事件」(宮崎文夫被告)、2017年6月に起きた「東名高速追突事故」(石橋和歩被告)は、理解しがたい事件として記憶に新しいでしょう。
自動運転化すれば、相手の車を路上に停めさせるなんてことはできませんし、信号待ちで車から降りて文句を言うこともできなくなります。
窓を開けて暴言を吐くのがせいぜいとなるでしょう。
こちらの記事↓で詳しく解説しています。自動運転化普及の前にどうぞ。
運転士不足
人手不足という課題はどの業界でもあるものですが、特に運輸、観光業界は深刻で、ドライバー1人が受け持つスケジュールが過密すぎて事故を起こし、社会問題として取り上げられることも珍しくはなくなっています。
また、配送業者が商品を投げて届ける悪質な瞬間が偶然撮影、拡散された「炎上案件」があった事を記憶している人も多いでしょう。
それもすべては「人手不足」によるもので、自動運転化が全国的に導入されれば時間の調整も容易になりますし、配送員の負担も激減するでしょう。
自動運転化で伸びる産業がある

先ほど、衰退していくものがある事を述べましたが、逆に「伸びる産業」も出てくるのが世の常というものです。
過激な 分かり易い表現をするならば、「取って代わるもの」が今後伸びてくると言ってもいいのではないでしょうか。
自動車が馬車や人力車に取って代わられ、運転士という職業が生まれたように、新時代の舵取りを担うであろう産業をピックアップしてみました。
人工知能
自動運転を語る上でかかせないのが、このハイテク産業です。
人間の知能をコンピューターで再現するという途方もない思想は、ついにここまで来ました。
車の運転には、車の構造、動き方、機能などを把握した上で道路交通法や歩行者の動き、自転車の動き、バイクの動き、他の車の動きを関連付け、膨大な情報を処理して最適な判断を瞬時に叩き出さなくてはなりません。
これらは人間にしかできない事とされてきましたが、AIに車の運転を任せるような領域にまで到達しているんです。
自動運転化が身近になればなるほど、この産業がアツくなるのは必然と言ってもいい位なのではないでしょうか。
交通ビッグデータ
自動運転化に際して、重要な情報が交通データです。
スタートからゴールまでの距離、時間、地形と、様々なデータを得る事で複雑な条件でもシステムが車を走らせる事が可能となってきます。
ナビゲーションとの連動で渋滞を避けたり、正確な到達時間を測れたりもできるでしょう。
こういった情報は鮮度が命で、自然災害で通行できなくなっている箇所がある場合などは即座に情報を共有する必要があります。
自動運転のネットワークを通じて、様々な情報のやり取りが行われるため、既得権益が絡んできそうですが、「多くの人が利用するモノにはビジネスチャンスがぶら下がっている」とも言えるでしょう。
各種センサー機器
自動運転を下支えしているのはたくさんのセンサー類であることは前述の通りですが、普及するということは、それだけ「需要が見込める」ことでもあります。
軍事品評会なるものがあるそうで、そこに世界各国の戦車が集まり、名だたる評論家たちが品評するなかで、砲身の先端にお盆を取り付け、そこにワインの入ったグラスを置き、一周回転させてこぼれなかったのは日本の戦車だけだったという話があります。
この精度に世界が絶賛する一方、日本の技術力に恐怖すら抱いたと言います。
日本はこういった精密機械の産業を強くしてきた経緯があり、「made in Japan」は世界で高い評価を得ています。
自動運転の普及に合わせ、この特性が今後武器となり、クルマ作りにおいて世界に誇れるトップクオリティを実現させるでしょう。
配送業
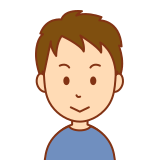
「え、さっき衰退するって言ってなかった?」
いえ、衰退するのは事業ではなく、ドライバーや配送員なんです。
配送事業でいえば、逆に伸びる可能性があります。
ネット通販大手のAmazonがやっていた「即日配送サービス」。
注文して1日以内に商品が届くという業界では型破りなサービスがありましたが、Amazonが配送業者に負担を強いていたことが問題になりました。
が、あれがまた再現されるかもしれません。
というのも、すべてを人が担当していたから無理がかかって問題になってしまったわけで、運転が自動になれば、配送スタッフは車から顧客の届け先に商品を持っていくだけ。
これなら大幅な人事整理、サービスの質の向上も期待できることから、成長産業の一つになるのではないか、と期待されています。
自動車保険
自動運転化とは言え、車は事故のリスクが伴います。
そのリスクを軽減させるために「保険」があるとするなら、自動車保険の有り方もガラッと変わってくるのではないでしょうか。
完全な自動化にはまだまだ先の話になりそうですが、それでも交通の面においてバイクや自転車、歩行者は自動化されにくいでしょう。
なので事故のカテゴリーとしては、故障、非自動化なものとの接触、自然災害と、かなり絞り込めることから簡素化が可能になり、掛け金もリーズナブルな設定になってくると思われます。
また、非自動化の自動車に対しては、自動運転車が高額なことから保険料が割高になることが考えられます。
以上を踏まえると、伸びるというよりは「安定需要がある」業界として今後も発展していくでしょう。
この記事↓では、転職のカウンセリングについても触れています。併せてどうぞ。
自動運転化でトヨタがGoogleに勝てなくなる!?

長年にわたって日本の産業を支え、世界にそのクオリティを認めさせるにまでなった日本製自動車。
中でも最大手のトヨタ自動車は、国産メーカーでも頭一つ抜きんでている企業として有名です。
そのトヨタでさえ、自動運転車という部類においては、危機感を募らせていると言います。
なぜか、それは「戦う相手がGoogleになるかもしれないから」です。
Google社は自動運転のインフラが整っている
2020年現在、最もAIを効率的に使っている企業。
それこそGoogle社ではないでしょうか。
自動運転というものは、まず「大量のデータ」を必要とします。
自動車の運転に係わるデータ、道路のデータ、交通量のデータ、とにかくありとあらゆるデータを集めます。
そして、そのデータをAIが処理して分析、自動運転に適した情報に整えます。
自動運転が実行されるときは、整えたデータを使う事で安全で快適な運航が可能になる、というのがおおまかな流れです。
ここまででも、自動運転がインフラとして普及した場合のキモとなるモノがGoogleにはほぼ揃っている事にお気づきでしょうか。
まず、AI。「O.K. Google」と音声認識で呼びかければ、文字入力の代わりに声で検索が可能なことは広く知られていますね。
スマートスピーカーなるモノまで普及していることからも、いかにGoogleがAIに力を入れているかが伺えます。
また、データに関しても「Google MAP」を持っているので、地図データや交通のデータを膨大な量で保有しているんです。
そして極めつけが、androidという基盤となる「OS」(オペレーションシステム)を握っているということです。
これをなくして私達はソフトウェアが使えないほどのインフラを押さえているんです。
Googleも一枚岩ではない

実は、実験段階ですがGoogleは独自に完全な自動運転車を作っているんです。
実験段階のため課題も多いのですが、このタイミングでGoogleの社内情勢が変化したことで自動運転事業に陰りが出始めました。
仕組みとしては専門的で難しくなるので、噛み砕いて言うと、まずGoogleが「アルファベット」という会社を「親会社」として設立させます。
そうすることでアルファベット社がGoogleの持ち株会社となり、大規模な人事と事業が移動します。
そこに自動運転を担う部門の統括責任者に自動車経営のプロフェッショナル、クラフチック氏が就任。自動運転の最高技術責任者のクリス・アームソン氏との折り合いの悪さが目立つ様になり、アームソン氏は辞任。
こうした経緯もあり、アルファベットは「自動運転事業の事実上の撤退」を発表しました。
言ってみれば、本部長と工場長の業務上の不仲のようなもので、居心地の悪さを感じた主要スタッフが「Google離れ」をおこし、そのうちの一人ジェームス・カフナー氏は現在、トヨタが設立したTRI(トヨタ・リサーチ・インスティテュート)という研究所のクラウドコンピューティング部門を総括しています。
このTRI、トヨタが人工知能を研究するために設立した施設で、自動運転はもちろん、屋内用ロボットの開発にも取り組んでいることから、さらなる事業展開を見据えていたことになります。
もしかすると自動運転でGoogleと渡り合う事も考えていたのかもしれないとさえ思えてきます。
まとめ

現在は、人間が行う運転動作の一部を自動化するに留まっていますが、法律の整備、技術の熟成、ビジネスモデルの確立など、強固に立ち塞がる壁を突破した時は、瞬く間に普及し、新時代の先駆け的な出来事として歴史に刻まれるでしょう。
自動運転化で変わる私達の暮らし
漫画や映画やアニメーションでしか表現されなかったことが、いよいよ現実味を帯びてきましたが、正直なところ賛否両論あるかと思います。
自動運転化で、人はもっと「自由」になれる可能性が一段と広がりました。
その反面、新時代に対する拒絶反応は必ずと言ってもいい位に起こるものですが、それは実際なってみないとわからない事が往々にしてあります。
ですが、確実に言えることは「便利になる」ということでありましょう。
文明が高度になっていくのは、生物の頂点に君臨する人間の特権とも言えるのではないでしょうか。
その特権を受け入れるか、受け入れずに別の道を進むのか。
今後の展開が注目される分野だけに、目が離せなくなりそうです。






コメント
[…] 車の自動運転ってぶっちゃけどうなの?メリットの影に潜む問題点も解説 […]
[…] 車の自動運転ってぶっちゃけどうなの?メリットの影に潜む問題点も解説 […]