こんにちは。塾長です。
雑学と言うものは、必ずしも有益なモノとは限りませんが、何となく知っていた知識が意外な所で役に立ったという経験、思い当たる人も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな役に立つかもしれない無駄知識「雑学」を車にテーマを絞って紹介していきます。
車の「キンコン音」、これが分かれば40代以上!?

40代以上のドライバーにとっては、「昔懐かし」ですね。
これは、昭和の車の「速度警告音」なんです。
普通車は100km/h以上、軽自動車は80km/h以上になると「キンコン♪」と警告音が鳴るように設定されていました。
だいたい昭和終盤(昭和62~63年頃)から平成元年にかけて人知れず廃れていったかのように無くなっていきました。
その背景として、当時の輸入車メーカーの要望と、「眠気を誘発する危険性」が高まったためとされています。
当時のアメリカの人には、この「キンコン音」は受けなかったんですね。アメリカ政府から「この警告音を外してくれ」的なことを要求されたことで決定的になったようです。
因みに、この警告音は当時法律的にも保安基準第46条第2項で「義務付け」されていましたが、1986年に項目ごと削除されています。そこまでしなくても…という気がしないでもないですね。
MT車は、クラッチ操作無しでもシフトチェンジができる

エンジンの回転力を変速機(トランスミッション)を通してタイヤに伝えることでクルマは動きます。
このトランスミッションには大小たくさんの歯車がかみ合う事で加減速やバックができるようになり、回転力を伝えるということは歯車も回転しています。
通常はクラッチ操作で一時的にニュートラル状態をつくる事で、回転している歯車に干渉せずシフトチェンジをしますが、エンジンの回転数と、歯車の回転数が合わさる「領域」が存在します。
その領域にあれば、クラッチ操作せずにニュートラルにでき、タイミングが正確であればそのままシフトUPができます。
シフトダウンするには、ニュートラルにした時にアクセルをふかして回転数を上げ、一段下の「領域」に合わせる事でシフトダウンができます。
良い子 優良ドライバーの皆さんはマネしないでくださいね。
ボンネットの左先端についている「棒」、何のため?
ボンネットの左先端に棒が付いている車、ちょくちょく見かけると思います。
あの棒の名前は「コーナーポール」といって、助手席側のボンネットの端っこについています。
ドライバーから最も遠く、感覚が掴みづらいボンネットの距離を測る目安として考え出されたアイテムで、特に視力が低下した高齢者向けの設備として流通した経緯もあり、「コーナーポールの車=高齢者ドライバー」という偏見を生み出してしまいました。
ATの「Nレンジ」には本来の用途があった
AT、MT問わずに設けられている「ニュートラルポジション」。
トランスミッション内部の歯車を傷めずにシフトチェンジするマニュアル車はともかく、自動で変速できるAT車にもある事が不思議ではありませんか?
「言われてみれば」となる人も多いでしょう。
でも、ないと困る事になります。
それは、「緊急時のための設備」だからです。
「ニュートラル」は「トランスミッション内部のどの歯車にも触っていない状態」を言い、自動で変速するAT車には不必要な設備と思われがちです。
が、思いがけないトラブルで車が停止してしまった場合、安全を確保した上で車を路側帯等の安全な場所まで移動させなければなりません。
その際は人力で動かすことになる場合が多いですが、ニュートラル以外のポジションにシフトがある場合、車は動きません。
オモチャのミニカーと同じ状態になる事で初めて人力で動かすことが可能になるわけです。
とはいえ、軽自動車でも数百kgもの鉄の塊です。
一人で動かすのは相当の腕力と体力と気力と根性が要求されますので、先ずは助けを求めましょう。
因みに駆動方式がFR、MR、4WDの場合は、レッカー移動の際にニュートラルにしないとフロントを持ち上げての移動は出来なくなります。
車のドアノブに「バータイプ」が多くなったのは?

このタイプのドアノブが採用されているのは「高級車」が主流でした。
しかし、最近では一般大衆車と言われる車種にも続々採用され、軽自動車にも採用が多くなってきました。
これには二つの理由があります。
一つは、利便性とデザインがウケるようになった事が挙げられます。
従来の指を引っ掛けて押し上げる「フラップタイプ」と違い、指が上からも下からも入る事で開けやすさの幅が広がった事に加え、握る事が出来るため、握力の弱い女性や高齢者にも優しい効果があります。
また、軽自動車のハイト化に伴い、開けやすさを突き詰めた結果とも言えます。
さらに車体フォルムを損なうことなくアクセントになることから、デザインとしても優秀で、機能とデザインの両立がバランスされたドアノブと言って良いでしょう。
もう一つは、横転事故など車体が歪むほどのダメージを負った場合、乗員救助にドアノブにワイヤーを通してこじ開けることが可能、というレスキューの利点もあります。
あまり考えたくないものですが、参考までに。
自動車メーカーにちなんだ地名がある

「愛知県豊田市」はトヨタのお膝元として有名ですね。そこを走る車は殆どトヨタです。
それ以外にも、群馬県太田市にある「スバル町」、大阪府池田市にある「ダイハツ町」が知られています。
特にスバル町は、元々富士重工業(スバルの前社名)の敷地だったそうで、当時の市長から「スバルを市のPRに活かしたい」「スバルを応援したい」というメッセージと共に町名変更を発案された経緯があります。
因みに、スバル町の住民はいないそうです。
冷房と暖房、燃費に影響が大きいのは?

一般家庭のエアコンは、総じて暖房の方が電気代がかかるとされています。
では、車のエアコンはどうでしょうか。
実は冷房の方が燃費に影響が大きいんです。
つまり、冷房の方が燃料代がかかるのです。
なぜならば、暖房は「エンジンの熱」が利用でき、冷房は「エンジンの熱」が邪魔になるからです。
暖房の場合は、エンジンで熱せられた冷却水に風を送る事で温かい風が車内に届く仕組みです。エンジンの「排熱」を利用しているので、燃費の影響は少ないと言えます。
一方、冷房はコンプレッサーを作動させ、温められた空気を冷やす仕事が追加されます。
そのコンプレッサーはエンジンと連動しているため、作動中はエンジンの回転がやや上がります。
暖房でも霜取りの為にエアーコンディショナー(A/Cのボタン)を起動させた場合はコンプレッサーが作動し、除湿機能が働くためエンジン回転がやや上がり、燃費に影響が出ます。
ヘッドレストは役割があった

仮眠するのにシートを倒して、ヘッドレストを少し上げれば、丁度いい枕になりますね。
「ヘッドレスト」と言うだけあって、「頭の休憩所」的なニュアンスで「枕」の代わり程度に考えている人が大半ではないでしょうか。
実は、ヘッドレストには適正位置があり、正しい運転姿勢の時に少し「押される位置」まで上げるのが正しいとされています。
それは、追突などで首に急激なショックが加わる事でなる「むち打ち症」を防ぐためです。
首は5~6kgの頭を常に支えています。
加えて、脳から伸びる脊髄と一緒になっているとても大事な所です。
そんな人の「急所」を守る役割があるのです。
降雪地域でワイパーを立てる意味は?

雪かきをしなければならないほどの降雪量がある地域では、冬に駐車している車のほとんどは、ワイパーを立てています。
それは、「雪の重さでワイパーが曲がったり折れたりするのを防ぐため」です。
雪はフロントガラスに沿って斜めに積もります。
その積もった雪の量次第では、華奢なワイパーは簡単に折れてしまいます。
それを防ぐための「生活の知恵」なんですね。
まとめ
昔のネタから専門的なことまで幅広く紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
知っている方も知らなかった方も、少しでも「役に立ちそう」「おもしろかった」と思っていただけたら、うれしいです。



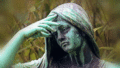
コメント
[…] 知られざる車の雑学!あなたはどれだけ知っていますか!? […]